イタチは何を食べる?【小動物や昆虫が主食】食性を理解して、効果的な餌付き防止策を立てる3つのポイント

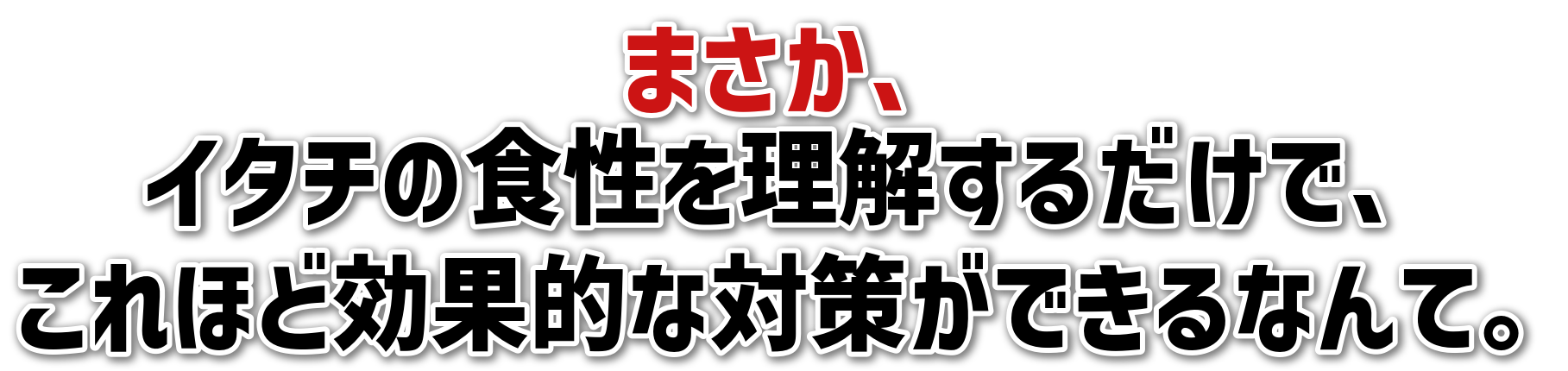
【この記事に書かれてあること】
イタチの食生活、気になりませんか?- イタチの主食は小動物と昆虫
- 季節によって食性が変化する特徴
- 人間の食べ物にも興味を示すため注意が必要
- イタチの1日の食事量は体重の15〜20%
- 高タンパク質の栄養バランスを好む傾向
- 食べ物の匂いを消すことが効果的な対策
- 代替餌場の設置で住宅地への侵入を防ぐ
実は、イタチの食べ物を知ることが、効果的な被害対策の第一歩なんです。
小動物や昆虫が大好物のイタチさん、でも人間の食べ物にも興味津々。
そんなイタチの食性を徹底解剖!
季節で変わる好みや、驚きの食事量まで、知れば知るほど面白いイタチの食生活。
さらに、その知識を活かした被害対策の秘策もご紹介。
「イタチよ、お引き取りください!」そんな願いを叶える鍵が、ここにあります。
イタチと上手に付き合うコツ、一緒に学んでいきましょう!
【もくじ】
イタチは何を食べる?生態と食性を徹底解説

イタチの主食は「小動物と昆虫」!肉食性の本能
イタチの主食は、小動物と昆虫です。肉食動物としての本能がしっかり息づいているんです。
イタチの食卓には、ネズミやモグラといった小さな哺乳類がよく並びます。
「今日のおかずはネズミさんかな?」なんて言いながら、イタチくんは狩りに出かけるわけです。
鳥の卵やカエル、トカゲなども大好物。
さらに、甲虫やバッタなどの昆虫もイタチにとっては絶品のごちそうなんです。
イタチの食生活を例えると、こんな感じです。
- 朝食:モグラのミンチ和え
- 昼食:カエルの唐揚げ
- おやつ:バッタチップス
- 夕食:ネズミの丸焼き
実は、イタチも時々果物や木の実を食べるんです。
特に甘いブドウや野イチゴが大好き。
でも、あくまでおまけ程度。
「デザートは果物で決まり!」くらいの感覚です。
イタチの体は、この肉食中心の食生活にぴったり。
鋭い歯と爪、細長い体型は、小動物を追いかけて捕まえるのに最適なんです。
まさに、自然が作り上げた完璧な肉食ハンターというわけ。
イタチの食性は季節で変化!春夏秋冬の好物を紹介
イタチの食卓は、季節によってガラリと変わります。まるで、四季折々の旬の食材を楽しむグルメのよう。
それぞれの季節で、イタチくんの好物が変化するんです。
春から夏にかけては、イタチにとって「ごちそうの季節」。
ネズミや鳥の卵、昆虫がたっぷり。
「今日はネズミのつかみ取り大会だ!」なんて、イタチくんはわくわくしているかも。
特に繁殖期には、タンパク質とカルシウムが豊富な食べ物を好んで食べます。
秋になると、イタチの食生活にちょっとした変化が。
果実や木の実も積極的に食べ始めるんです。
「冬に備えて、ビタミンも摂らなきゃ!」って感じでしょうか。
冬は、イタチにとって一番厳しい季節。
食べ物が少なくなるので、より小型の獲物や冬眠中の小動物を探して食べます。
「おーい、眠っているネズミさーん」なんて呼びかけているかも。
イタチの季節ごとの食事メニューを見てみましょう。
- 春:鳥の卵、若いネズミ、新芽を出したばかりの昆虫
- 夏:ネズミ、カエル、トカゲ、昆虫の大盛り
- 秋:ネズミに加えて、熟した果実や木の実
- 冬:小型の獲物、冬眠中の小動物、時には魚も
自然の中で生きる知恵が、ここにも表れているというわけです。
人間の食べ物にも興味あり!家屋侵入の原因に注意
イタチは、人間の食べ物にも興味津々なんです。「あれ?なんだかおいしそうな匂いがする!」って感じで、家の中に侵入してくることも。
これが、イタチによる被害の一因になっているんです。
イタチは「日和見食性」という特徴を持っています。
これは、「おいしそうなものがあれば何でも食べちゃう」という性質のこと。
人間の食べ物の中でも、特に肉類、魚、卵、チーズなどのタンパク質が豊富な食品に目がないんです。
「イタチくんの食べ物ランキング」を見てみましょう。
- 第1位:生肉(ハム、ソーセージなども大好物)
- 第2位:魚(干物や缶詰も狙われます)
- 第3位:卵(生卵も茹で卵も大歓迎)
- 第4位:チーズ(香りの強いものほど魅力的)
- 第5位:果物(甘いものが特に人気)
ゴミ箱や保管の悪い食品に引き寄せられて、「今日はどんなごちそうがあるかな?」なんて、勝手に家の中を探検しちゃうわけ。
でも、イタチが来るのは食べ物だけが理由じゃありません。
暖かく安全な住処を求めて侵入することもあるんです。
「ここなら雨風しのげそう」「子育てにぴったりの場所だな」なんて考えているかも。
だから、イタチ対策には食べ物の管理が大切。
ゴミはしっかり密閉し、食品は適切に保存。
「ここは餌場じゃないよ!」ってイタチに伝えることが、被害を防ぐ第一歩になるんです。
イタチに食べ物を与えるのは「逆効果」!絶対NG行動
イタチに食べ物を与えるのは、絶対にやってはいけません。これ、超重要ポイントです。
「かわいそうだから」って餌をあげると、大変なことになっちゃうんです。
まず、イタチに人間の食べ物を与えると、イタチの栄養バランスが崩れちゃいます。
「人間の食べ物、おいしい!」って喜んで食べるかもしれませんが、実はイタチの体にはあまり良くないんです。
イタチの胃腸は野生の食べ物に適応しているので、人間の食べ物を消化するのは大変。
最悪の場合、健康を害する可能性もあるんです。
次に、餌付けするとイタチが人間に慣れすぎちゃうんです。
「人間=食べ物くれる」って覚えちゃうと、どんどん人家に近づいてくるようになります。
結果、野生での生存能力が低下しちゃうんです。
「人間に頼りきりになっちゃった…」なんて、イタチくんの将来が危うくなっちゃいます。
イタチに餌をあげると、こんな悪影響が…
- 栄養バランスの崩れによる健康被害
- 野生での生存能力の低下
- 人家への依存度増加
- イタチの個体数増加による生態系のバランス崩壊
- 近隣住民とのトラブルの原因に
そんな時は、イタチが自然の中で生きていける環境を守ることが大切です。
例えば、庭に小さな池を作って魚を放すとか、果樹を植えるとか。
そうすれば、イタチくんも「自分で食べ物を見つけられた!」って喜ぶはず。
結局のところ、イタチと人間が適度な距離感を保つことが、お互いにとって一番いいんです。
「近すぎず、遠すぎず」がイタチとの付き合い方のコツ、というわけです。
イタチの食事量と栄養バランスを解明

イタチvs他の小動物!1日の食事量を比較
イタチの食事量は、体重の15〜20%にもなるんです。これって、他の小動物と比べるとどうなの?
驚きの事実が見えてきますよ。
まず、イタチの食事量について詳しく見てみましょう。
体重300グラムのイタチさんなら、1日に45〜60グラムの食事をとるんです。
「えっ、そんなに食べるの?」って思いましたよね。
これ、人間に例えると60キロの大人が9〜12キロの食事を毎日とるようなものなんです。
すごい食欲ですよね。
では、他の小動物と比べてみましょう。
- ネズミ:体重の10〜15%
- リス:体重の5〜10%
- ハムスター:体重の8〜12%
- ウサギ:体重の6〜8%
「イタチさん、食べ過ぎじゃない?」って言いたくなっちゃいます。
でも、これには理由があるんです。
イタチは代謝が非常に速いんです。
体が細長くて表面積が大きいため、体温を維持するのに多くのエネルギーを必要とするんです。
だから、たくさん食べないと生きていけないんです。
イタチの食事風景を想像してみてください。
「もぐもぐ、ごくごく」と、小さな体で懸命に食べる姿。
まるで、お腹をすかせた子どもがおやつを食べているみたい。
でも、これが彼らの生きる知恵なんです。
この大食漢ぶりが、実は人間との軋轢を生む原因にもなっているんです。
家の周りに食べ物があると、イタチはそれを逃すまいと必死になるんです。
「ここは宝の山だ!」って喜んでいるかもしれません。
だからこそ、イタチ対策には食べ物の管理が欠かせないんです。
イタチさんの食欲を理解すれば、より効果的な対策が立てられるというわけ。
イタチの理想的な栄養バランス!高タンパクが鍵
イタチの理想的な食事は、高タンパク質、中程度の脂質、低炭水化物。この黄金比が、イタチの健康と活力の秘訣なんです。
具体的な数字で見てみましょう。
イタチの理想的な栄養バランスは、タンパク質50%、脂質30%、炭水化物20%。
これって、人間の食事バランスとはだいぶ違いますよね。
「えっ、炭水化物こんなに少ないの?」って驚く人も多いはず。
イタチの食事をイメージしてみましょう。
- 朝食:ネズミのたたき(タンパク質たっぷり)
- 昼食:カエルの刺身(低脂肪高タンパク)
- おやつ:甲虫のから揚げ(タンパク質と適度な脂質)
- 夕食:鳥の卵とトカゲのミックス丼(タンパク質と脂質のバランス◎)
「まるで筋トレマニアの食事みたい!」って思いませんか?
でも、なぜイタチはこんなに高タンパクな食事を必要とするんでしょうか。
それは、イタチの活発な生活スタイルと関係があるんです。
イタチは常に動き回り、狩りをし、時には木に登ったり泳いだりします。
「忙しい忙しい!」って言いながら、あっちこっち動き回っているイメージです。
この活発な生活を支えるには、筋肉を維持し、エネルギーを効率よく生み出す必要があります。
そのために、高タンパク質の食事が欠かせないんです。
タンパク質は筋肉の材料になるだけでなく、体の様々な機能を維持するのに重要な栄養素なんです。
一方で、炭水化物の摂取量が少ないのは、イタチの消化器系が主に肉食に適応しているからです。
「パンよりお肉!」がイタチのモットーみたいなものですね。
この食事バランスを知ることで、イタチ対策にも役立ちます。
例えば、イタチを引き寄せないためには、タンパク質の多い食品の管理に特に気をつける必要があるんです。
「ゴミ箱の中身、タンパク質多くない?」って、ちょっと意識してみるのも良いかもしれません。
イタチの食欲は季節で変動!夏と冬で大きな差
イタチの食欲は、季節によってガラリと変わるんです。夏はモリモリ食べて、冬はちょっぴり控えめ。
まるで、季節ごとに違う性格になっちゃうみたい!
夏のイタチさんは、まさに大食漢。
冬の1.5倍も食べちゃうんです。
「夏バテ知らずのイタチさん」って感じですね。
なぜこんなに食べるかというと、夏は活動量が圧倒的に多いからなんです。
暑い中を動き回るので、たくさんのエネルギーが必要になるんです。
夏のイタチの1日を想像してみましょう。
- 朝:「今日も暑いなぁ。でも食べなきゃ!」とネズミを2匹ペロリ
- 昼:「暑さに負けるな!」と虫を100匹以上パクパク
- 夕:「疲れたー。でもお腹すいた!」と鳥の卵を3個ゴクゴク
「おいおい、食べ過ぎじゃない?」って思っちゃいますよね。
一方、冬のイタチさんは少し控えめ。
寒さで体を動かすのが億劫になるので、活動量が減るんです。
それに伴って、代謝も落ちるので、必要なエネルギー量も減少。
「寒いから、ちょっとだけ食べよっと」って感じでしょうか。
冬のイタチの食事はこんな感じ。
- 朝:「寒いなぁ。少しだけ食べよう」と小さなネズミ1匹
- 昼:「あんまり動きたくないなぁ」と虫を50匹くらい
- 夕:「今日はもう寝よっかな」と鳥の卵1個だけ
この季節による食欲の変化は、イタチ対策を考える上でとても重要なんです。
夏は特に気をつけないと、イタチさんが家の周りの食べ物を狙って頻繁に現れるかもしれません。
「夏はイタチ警戒警報発令中!」って感じで、食べ物の管理に気をつける必要があります。
一方、冬はイタチの活動が少し落ち着くので、対策も少し楽になるかもしれません。
でも、油断は禁物。
「冬だからって安心しちゃダメよ」ってことです。
季節によるイタチの食欲の変化を知ることで、より効果的な対策が立てられるんです。
「今の季節、イタチさんはお腹すいてるかな?」って考えながら対策を立てると、的確な対応ができるというわけ。
イタチの食事量と体重の関係!過剰摂取のリスク
イタチの食事量と体重には、密接な関係があるんです。適切な食事量を保つことが、イタチの健康にとって超重要。
でも、時には過剰摂取のリスクも…。
まず、イタチの標準的な体重は約200〜300グラム。
この体重を維持するには、1日に体重の15〜20%、つまり30〜60グラムの食事が必要なんです。
「えっ、そんなに食べるの?」って驚きますよね。
人間に例えると、60キロの人が毎日9〜12キロも食べるようなものなんです。
ここで、イタチの体重管理表を見てみましょう。
- やせ気味:200グラム未満(食事量が少なすぎる可能性)
- 標準体重:200〜300グラム(ちょうど良い食事量)
- 太り気味:300グラム以上(食べ過ぎの可能性)
「ぼく、ちょっと太っちゃったかな?」なんて、気にしてるイタチもいるかもしれません。
では、過剰摂取のリスクって何でしょうか。
実は、野生のイタチが必要以上に食べ過ぎてしまうケースがあるんです。
特に、人間の食べ物に手を出してしまった場合に起こりやすいんです。
例えば、ゴミ箱あさりが習慣になったイタチさん。
「人間の食べ物、おいしいなぁ」って思っちゃって、どんどん食べ過ぎちゃうんです。
すると、こんなリスクが…。
- 肥満:動きが鈍くなり、天敵から逃げられなくなる
- 栄養バランスの乱れ:野生での生存能力が低下
- 人間への依存:自然界での食事を忘れてしまう
- 病気のリスク増加:免疫力の低下や消化器系の問題
だからこそ、イタチが人間の食べ物に手を出さないようにすることが大切なんです。
ここで、イタチ対策のポイントが見えてきます。
食べ物の管理をしっかりすることで、イタチの過剰摂取を防ぎ、健康的な野生生活を送れるようサポートできるんです。
「イタチさんの健康のためにも、ゴミ箱はしっかり閉めよう!」って感じですね。
結局のところ、イタチの食事量と体重の関係を知ることは、イタチとの共存を考える上で重要なヒントになるんです。
イタチさんの健康を考えながら対策を立てることで、より効果的で人道的な方法が見つかるかもしれません。
「イタチさんも、私たちも、みんなハッピーになれる方法」を探すきっかけになるというわけです。
イタチ対策!食べ物を通じた被害予防と撃退法

食べ物の匂いを消す!イタチを寄せ付けない保存方法
イタチを寄せ付けないために、食べ物の匂いを消すことが超重要です。正しい保存方法で、イタチさんに「ここには美味しいものないよ」とアピールしちゃいましょう。
まず、イタチの鼻はとっても敏感。
人間の100倍以上の嗅覚を持っているんです。
「わー、人間には気づかない匂いもバレバレじゃん!」って感じですよね。
だからこそ、匂い対策が大切なんです。
では、具体的な対策を見ていきましょう。
- 密閉容器の活用:食品は必ず密閉容器に入れましょう。
「ぴちっ」と音がするくらいしっかり閉めるのがコツです。 - 二重包装:生ゴミは二重に袋に入れて、さらに蓋付きのゴミ箱に入れます。
「念には念を入れて」というやつです。 - 冷蔵庫の活用:匂いの強い食品は冷蔵庫に入れましょう。
「冷たくて匂いも少ない」で一石二鳥です。 - こまめな掃除:食べこぼしはすぐに拭き取りましょう。
「ちょっとくらいいいや」は禁物です。 - 消臭スプレーの使用:キッチンや食品保管場所に消臭スプレーを使うのも効果的。
「さわやかな香りで匂いをマスク」作戦です。
そうすれば、家に近づく回数も減るはず。
でも、注意点もあります。
市販の芳香剤や香水を使いすぎるのは逆効果。
強い人工的な匂いは、イタチの好奇心をくすぐってしまう可能性があるんです。
「なんだこの匂い?調べてみよう」って思われちゃうかも。
結局のところ、「匂いを消す」というのは「イタチさんに気づかれない」ってことなんです。
まるで、忍者のように存在を消すイメージですね。
「ここには何もおいしいものはないよ〜」って、そっと囁きかけるような感じで対策を進めていくのが効果的なんです。
イタチvsネコ!餌付け対策の違いに要注意
イタチとネコ、どちらも可愛らしい動物ですが、餌付け対策は全然違うんです。間違えると大変なことに!
それぞれの特徴を理解して、適切な対策を取りましょう。
まず、イタチの餌付けは絶対にNG。
「かわいそうだから」って餌をあげると、どんどん人間に慣れてしまい、家に侵入する回数が増えちゃうんです。
「おっ、ここにごはんがあるぞ!」って、イタチさんが毎日やってくるようになっちゃいます。
一方、ネコの場合は地域によっては餌付けが認められていることも。
でも、むやみに餌をあげるのはやっぱり問題です。
野良ネコが増えすぎたり、糞尿被害が増えたりする可能性があるからです。
では、イタチとネコの餌付け対策の違いを比べてみましょう。
- イタチの場合:
- 絶対に餌を与えない
- 食べ物の匂いを徹底的に消す
- ゴミ箱や保管場所をしっかり密閉
- 果樹や野菜畑にはネットを張る
- ネコの場合:
- 地域のルールに従って適切に餌を管理
- 餌やりをする場合は決まった時間と場所で
- 食べ残しはすぐに片付ける
- 不妊去勢手術を推奨
一方、ネコの場合は「適切な管理のもとで共存」という考え方になります。
面白いのは、イタチ対策がネコ対策にもなることがあるということ。
例えば、ゴミ箱をしっかり閉めるのは、イタチにもネコにも効果があるんです。
「一石二鳥」ってやつですね。
でも、気をつけたいのが香り対策。
イタチは強い香りが苦手ですが、ネコは香りに敏感で逆に引き寄せられることも。
「あれ?イタチ対策のつもりがネコを呼んじゃった?」なんてことにならないよう注意が必要です。
結局のところ、イタチもネコも野生動物。
人間との適切な距離感を保つことが、お互いにとって一番いい関係なんです。
「仲良く、でも程よく」が理想的な付き合い方、というわけです。
代替餌場作戦!イタチを住宅地から遠ざける裏技
イタチを住宅地から遠ざける秘策、それが「代替餌場作戦」です。イタチさんの好みを逆手に取って、「こっちの方がおいしいよ」って誘導しちゃう作戦なんです。
まず、この作戦のポイントは場所選び。
家から50メートルほど離れた、人家のない場所を選びます。
「ちょっと遠いけど、行く価値あり!」とイタチさんに思わせるのがコツです。
次に、餌の選び方が重要です。
イタチの大好物リストを見てみましょう。
- 小魚(イワシやアジなど)
- 鶏肉の切れ端
- ゆで卵
- 果物(ブドウや野イチゴなど)
- ドッグフードやキャットフード
「わー、ごちそうがいっぱい!」ってイタチさんが喜ぶ姿が目に浮かびますね。
ただし、注意点もあります。
- 餌は腐りにくいものを選ぶ
- 量は控えめに(食べきれる量だけ)
- 近隣住民に理解を求める(「イタチ対策なんです」と説明)
- 定期的に場所を少しずつ変える(イタチを徐々に遠ざける)
- 他の野生動物を誘引しないよう注意
「あれ?効果ないかな?」って焦らずに、根気強く続けることが大切です。
面白いのは、この作戦を続けていくうちに、イタチの行動パターンが見えてくること。
「あ、この時間にいつも来てるな」とか「この餌が一番人気みたい」とか、イタチ博士になった気分を味わえるかも。
でも、くれぐれも餌付けではないことを忘れずに。
あくまで「住宅地から遠ざける」のが目的。
イタチさんに「ここが新しいレストランだよ」って教えてあげるイメージです。
この作戦、うまくいけばイタチの住宅地侵入が減少。
人間もイタチも、お互いにハッピーな関係が築けるかもしれません。
「みんなで仲良く、でも適度な距離感で」という理想的な共存が実現できるんです。
スパイス作戦!イタチ撃退に効く香辛料活用法
イタチ撃退に香辛料が効果的?そう、これが「スパイス作戦」です。
イタチさんの敏感な鼻を利用して、「ここはちょっと苦手かも」と思わせちゃう作戦なんです。
まず、イタチが苦手な香辛料リストを見てみましょう。
- 唐辛子
- 黒コショウ
- カイエンペッパー
- ガーリックパウダー
- シナモン
イタチさんもきっと「くしゅん!」ってなっちゃうはず。
では、具体的な使い方を見ていきましょう。
- スパイス水スプレー:香辛料を水に溶かしてスプレーボトルに入れます。
イタチの侵入経路や好む場所に吹きかけます。 - スパイスパック:小さな布袋に香辛料を入れて、イタチの通り道に置きます。
- スパイスライン:粉末の香辛料で、庭の境界線や窓際にラインを引きます。
- スパイスボール:香辛料を丸めて、イタチの巣穴の近くに置きます。
強すぎる刺激はイタチにとってストレスになるかも。
「イタチさん、ごめんね」って気持ちを忘れずに、程よい使用を心がけましょう。
面白いのは、この作戦、人間にとっても良い香りになること。
「え?イタチ対策なのに家中いい香り?」なんて驚きの効果があるんです。
まるで、おしゃれな芳香剤を使っているみたい。
ただし、注意点もあります。
- ペットや小さな子供がいる家庭では使用を控えめに
- アレルギーのある人は事前に確認を
- 食用の香辛料を使うこと(農薬入りのものはNG)
- 雨や風で流されやすいので、定期的な再散布が必要
「一石二鳥」どころか「一石三鳥」かも。
イタチさんには「ごめんね」と言いつつ、人間にとっては快適な環境作りにもなるんです。
結局のところ、イタチと人間、お互いの生活圏を上手に分けることが大切。
「イタチさんはお外で、人間はお家で」という関係が理想的。
スパイス作戦で、そんな関係が築けるかもしれませんね。
イタチの食性を利用!長期的な被害対策のコツ
イタチの食性を知れば知るほど、効果的な対策が見えてくるんです。長期的な被害対策のコツは、イタチさんの「食べたい!」という気持ちを上手に利用すること。
まず、イタチの食性の特徴をおさらいしましょう。
- 主食は小動物と昆虫
- 高タンパク質の食事を好む
- 季節によって食べ物が変化
- 1日の食事量は体重の15〜20%
- 人間の食べ物にも興味あり
1. 環境整備
イタチの好物を減らすことが重要です。
例えば、ネズミの駆除をしっかり行うと、イタチの主食がなくなります。
「あれ?ごはんがないぞ」ってイタチさんが困惑するかも。
2. 季節に合わせた対策
春は繁殖期で特に警戒が必要。
タンパク質が豊富な食べ物の管理に気をつけましょう。
「赤ちゃんのためにごはんが必要なんだ!」って必死になっちゃうかもしれません。
3. 代替餌場の設置
家から離れた場所に、イタチの好物を置く作戦。
「こっちの方がおいしいよ」って誘導します。
でも、餌付けにならないよう注意が必要です。
4. 匂い対策の徹底
イタチの鋭い嗅覚を逆手に取ります。
食べ物の匂いを消すのはもちろん、イタチの嫌いな香りを利用するのも効果的。
「うーん、この匂い苦手だなぁ」ってイタチさんが思うような環境を作ります。
5. 物理的な侵入防止
イタチが入れそうな隙間をふさぎます。
直径3cm以上の穴があれば侵入可能なので、細かいチェックが必要です。
「えー、入れないよー」ってイタチさんがお手上げになるくらいしっかり対策しましょう。
これらの対策を組み合わせて、長期的に実施することが大切です。
「今日はダメだったけど、明日は入れるかも」ってイタチさんに思わせないようにするのがポイント。
面白いのは、この対策を続けていくうちに、イタチの行動パターンが見えてくること。
「あ、この季節はこんな行動をするんだ」とか「この時期は特に警戒が必要だな」とか、イタチ博士になった気分を味わえるかもしれません。
でも、忘れてはいけないのは、イタチも生きる権利がある野生動物だということ。
過度な排除ではなく、上手な「すみ分け」を目指すのが理想的です。
「イタチさんはお外で、人間はお家で」という関係が築けたら、それが一番の成功と言えるでしょう。
結局のところ、イタチ対策は「イタチの気持ちになって考える」のがコツ。
「食べたい」「安全に過ごしたい」というイタチの本能を理解した上で、人間とイタチ、お互いにとって快適な環境を作っていく。
そんな長期的な視点で対策を考えることが、本当の意味での「イタチ対策」なんです。