イタチによる畑の被害って?【根菜類や果菜類が主な標的】作物別の対策と、被害を未然に防ぐ5つの予防法

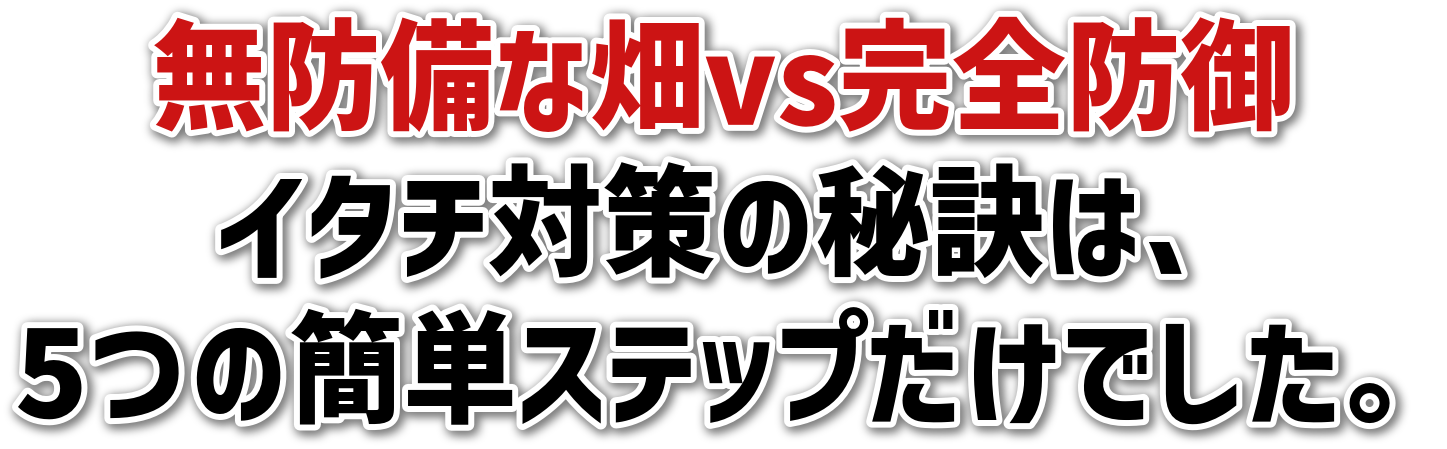
【この記事に書かれてあること】
畑仕事の喜びを台無しにするイタチの被害。- イタチは根菜類と果菜類を好んで食べる傾向がある
- 被害は夜間から早朝に集中し、最大で収穫量が50%減少する可能性も
- 小規模菜園は被害の影響が大きく、都市部と農村部で対策方法が異なる
- 1メートル以上のフェンス設置で侵入を90%阻止できる
- ハーブや天然素材を使った忌避剤で有機農法との両立が可能
でも、諦めないでください!
この記事では、イタチによる畑の被害の実態と、効果的な対策方法をご紹介します。
根菜類や果菜類が狙われやすいこと、夜間の被害に要注意なことなど、イタチの行動パターンを知れば、賢く対策を立てられるんです。
フェンス設置や天然忌避剤など、5つの効果的な方法で、イタチと上手に付き合いながら、豊かな収穫を目指しましょう。
「よし、今年こそイタチに負けない!」そんな気持ちで、一緒に対策を学んでいきましょう。
【もくじ】
イタチによる畑の被害の実態と特徴

イタチが好む作物は「根菜類と果菜類」が主な標的!
イタチは根菜類と果菜類を特に好んで食べます。これらの作物は栄養価が高く、イタチにとって魅力的な餌となるのです。
まず、根菜類についてお話しましょう。
ニンジン、ジャガイモ、サツマイモなどがイタチの大好物です。
「えっ、地中にある野菜なのに?」と思われるかもしれません。
でも、イタチは鋭い嗅覚を持っているんです。
地中の野菜の匂いを嗅ぎ分けて、ほじくり出して食べてしまうんです。
次に果菜類。
トマト、イチゴ、メロンなど、甘みのある果菜類もイタチの被害を受けやすいんです。
これらの野菜は地上にあるので、イタチにとっては簡単に手に入る美味しいごちそうなんです。
「まるでデザートみたいですね」とイタチは考えているかもしれません。
では、他の野菜はどうでしょうか?
- 葉物野菜(レタス、ホウレンソウなど):比較的被害は少ない
- 豆類:時々食べられることがある
- ネギ類:臭いが強いため、あまり好まれない
「うちの畑にはイタチの大好物がいっぱいあるぞ」と気づいたら、特に注意して対策を立てる必要があります。
根菜類と果菜類を重点的に守ることで、イタチの被害を効果的に減らすことができるんです。
被害の特徴は「不規則な形の食べ跡」に注目
イタチによる野菜の被害は、不規則な形の食べ跡が特徴です。この独特の痕跡を見つけたら、イタチの仕業だと考えてよいでしょう。
イタチは鋭い歯を持っています。
野菜を噛み砕くときに、ガリガリッと不規則な形で食べていくんです。
まるで「ジグザグパズル」のような食べ跡を残します。
「まあ、なんてむちゃくちゃな食べ方!」と驚くかもしれません。
では、具体的にどんな特徴があるのでしょうか?
- 噛み跡が深く、はっきりしている
- 食べ跡の形が不揃いで、でこぼこしている
- 野菜の一部だけが食べられている(丸ごと持ち去られることは少ない)
- 複数の野菜に少しずつ被害が出ている(一つの野菜を食べ尽くすことは稀)
「ん?この食べ跡、なんかヘンだぞ」と思ったら、イタチの仕業を疑ってみましょう。
他の動物との違いも知っておくと良いでしょう。
例えば、ウサギは歯形がきれいに残り、カタカタッと整った食べ跡になります。
ネズミは小さな歯形で、ちょこちょこっと齧った跡が特徴です。
イタチの被害に早く気づくコツは、毎日畑を見回ることです。
「今日はどんな変化があるかな?」とわくわくしながら観察すれば、イタチの被害もすぐに発見できますよ。
不規則な形の食べ跡を見つけたら、すかさずイタチ対策を始めましょう。
そうすれば、被害を最小限に抑えられるんです。
夜行性のイタチ!被害は「夜間から早朝」に集中
イタチは夜行性の動物です。そのため、畑への被害は夜間から早朝に集中します。
昼間はほとんど活動せず、日が沈むころから動き出すんです。
「え?じゃあ夜中に畑を見回らないといけないの?」と心配する必要はありません。
イタチの活動時間を知っておくだけでも、効果的な対策が立てられるんです。
では、イタチの夜間活動の特徴を見てみましょう。
- 活動開始時間:日没後30分〜1時間程度
- 最も活発な時間帯:真夜中(午後10時〜午前2時頃)
- 活動終了時間:日の出前(午前4時〜5時頃)
まず、暗闇で動き回るのが得意なんです。
目がキラリと光り、暗い中でもよく見えるんです。
「まるで夜の忍者みたい!」と言えるでしょう。
また、夜は天敵が少ないというメリットもあります。
鳥類などの捕食者は昼間活動するものが多いので、夜はイタチにとって安全な時間帯なんです。
この習性を利用して対策を立てましょう。
例えば、夕方に畑を見回り、イタチが好む野菜にカバーをかけるのが効果的です。
「おやすみなさい、大切な野菜たち」と言いながら守ってあげるんです。
朝一番での見回りも大切です。
「おはよう、無事だったかな?」と確認し、被害があればすぐに対処できます。
夜間用の防犯カメラを設置するのも良いアイデアです。
イタチの行動パターンを把握できれば、より効果的な対策が立てられるでしょう。
イタチの夜の活動を知ることで、あなたの畑を守る力が大きく向上しますよ。
被害を放置すると「収穫量が最大50%減少」の危険性
イタチによる畑の被害を放置すると、収穫量が最大50%も減少してしまう危険性があります。これは深刻な問題です。
せっかく手間ひまかけて育てた野菜が、半分も失われてしまうなんて考えられませんよね。
では、具体的にどのような被害が起こるのでしょうか?
- 根菜類の食害:地中からほじくり出されて食べられる
- 果菜類の食害:実がかじられ、味や見た目が損なわれる
- 茎や葉の損傷:野菜の生長が妨げられる
- 土壌の荒らし:根系が傷つき、植物の健康に影響
- 病気の媒介:イタチが運ぶ病原体で野菜が病気になる
実は、イタチは一晩で想像以上の被害を与えるんです。
小さな体でも、すばしっこく動き回るので、次々と野菜を食べてしまうんです。
特に小規模な家庭菜園では、被害の影響が大きくなります。
「今年の収穫を楽しみにしていたのに…」と落胆することになりかねません。
また、被害は単に収穫量の減少だけではありません。
残った野菜も質が落ちてしまうんです。
「見た目が悪くなっちゃった…」「味が落ちちゃった…」という事態に陥る可能性もあります。
さらに、イタチの被害を放置すると、他の害獣を引き寄せてしまう危険性もあります。
「イタチが来るなら、ここは餌場として良さそうだ」と、他の動物も寄ってくるかもしれません。
だからこそ、早めの対策が大切なんです。
「被害が小さいうちになんとかしよう」という心構えが重要です。
イタチの被害に気づいたら、すぐに行動を起こしましょう。
そうすれば、あなたの大切な野菜を守り、豊かな収穫を得ることができるんです。
イタチへの餌付けはやっちゃダメ!被害を拡大させる逆効果
イタチへの餌付けは絶対にやってはいけません。これは被害を拡大させる逆効果になってしまうんです。
「かわいそうだから餌をあげよう」という優しい気持ちが、実は大きな問題を引き起こすことになるんです。
なぜイタチへの餌付けがダメなのか、具体的に見ていきましょう。
- イタチが畑に頻繁に来るようになる
- イタチの繁殖が促進され、個体数が増える
- イタチが人間を恐れなくなり、より大胆になる
- 他のイタチも集まってくる可能性がある
- 野菜以外の被害(家屋侵入など)も増える
実は、餌付けは一時的に問題を解決するように見えて、長期的には大きな問題を引き起こすんです。
例えば、ゴミや生ごみを畑に放置するのも、間接的な餌付けになってしまいます。
「ちょっとぐらいいいか」と思って捨てたゴミが、イタチを引き寄せる原因になるんです。
また、収穫した野菜の残渣を畑に放置するのも逆効果です。
「肥料になるから」と考えるかもしれませんが、これもイタチの格好の餌場になってしまうんです。
さらに、イタチを見つけても素手で追い払おうとするのは危険です。
「シッシッ、行っちゃいなさい!」と近づくと、イタチの攻撃性が高まり、かえって危険な状況になる可能性があります。
では、どうすればいいのでしょうか?
まずは、畑と周辺をきれいに保つことが大切です。
「イタチさん、ここには餌はないよ」というメッセージを送るんです。
そして、イタチを見かけても決して餌を与えないようにしましょう。
「かわいそう」と思っても、自然の中で生きていく力を信じることが大切です。
餌付けをしないことで、イタチとの適切な距離を保ち、被害を最小限に抑えることができるんです。
あなたの畑を守るためにも、イタチへの餌付けは絶対に避けましょう。
イタチ被害の深刻度と比較

小規模菜園vs大規模農場!被害の影響はどちらが深刻?
小規模菜園の方が、イタチ被害の影響は深刻です。面積比で見ると、小さな畑ほど被害の割合が高くなってしまうんです。
「えっ、小さい畑の方が被害が大きいの?」と驚く方もいるかもしれません。
でも、よく考えてみると納得できますよね。
小規模菜園では、イタチが一晩で畑全体を荒らしてしまう可能性があるんです。
例えば、10平方メートルの小さな畑と、1000平方メートルの大きな農場を比べてみましょう。
イタチが両方の畑で同じ面積(例えば5平方メートル)を荒らしたとします。
小さな畑では半分が被害を受けてしまいますが、大きな農場では被害はわずか0.5%にすぎません。
被害の深刻さを具体的に見てみましょう。
- 収穫量への影響:小規模菜園では収穫量が半減することも
- 心理的影響:努力が水の泡になる失望感が大きい
- 経済的影響:自家消費用の野菜が食べられなくなる
- 対策の難しさ:予算や労力の制限で十分な対策が取りにくい
小規模菜園だからこそ、きめ細かな対策が可能なんです。
例えば、畑全体をネットで覆ったり、こまめに見回ったりできるでしょう。
大規模農場では面積が広すぎて、細かな対策が難しいこともあります。
「広いから大丈夫」と油断してしまうかもしれません。
でも、小規模菜園なら「我が子」のように愛情を込めて守れるんです。
小さな畑だからこそ、イタチ対策にも創意工夫が生きてきます。
「よーし、うちの畑は絶対守るぞ!」という気持ちで、イタチに負けない菜園づくりを目指しましょう。
小さくても、あなたの畑は大切な宝物なんです。
都市部vs農村部!イタチ被害の特徴と対策の違い
都市部と農村部では、イタチ被害の特徴と対策方法が大きく異なります。面白いことに、どちらの地域にも独自の課題と解決策があるんです。
まず、被害の規模から見てみましょう。
農村部の方が被害面積は広いですが、都市部の小規模菜園では被害の影響がより深刻に感じられる傾向があります。
「えっ、都市部にも畑があるの?」と思う方もいるかもしれませんが、ベランダ菜園や市民農園など、都市部でも野菜作りは盛んなんです。
それぞれの地域の特徴を比較してみましょう。
- 都市部:限られたスペース、近隣への配慮が必要
- 農村部:広い土地、自然環境との調和が重要
- 都市部の対策:
- コンパクトな防護ネットの設置
- 音や光を使った忌避装置(ただし騒音に注意)
- ベランダや屋上での栽培で接近を防ぐ
- 農村部の対策:
- 広範囲をカバーする電気柵の設置
- 天敵となる動物(犬や猫)の活用
- 周辺環境の整備(草刈りや餌場の除去)
都市部のイタチは人間に慣れていて、より大胆に行動することがあるんです。
一方、「田舎だからイタチだらけ」と諦めるのも早計。
広い土地を活かした対策で、被害を最小限に抑えられます。
都市部では近隣との協力が鍵になります。
「ご近所さんと一緒にイタチ対策!」なんて、コミュニティの絆を深めるチャンスかもしれません。
農村部では自然との共生を意識した対策が求められます。
「イタチさんにも住み処を残しつつ、我が畑は守る!」という姿勢が大切です。
地域の特性を活かしたイタチ対策で、どこでも美味しい野菜が育てられるんです。
都会でも田舎でも、あなたの畑を守る方法はきっと見つかりますよ。
イタチvsウサギ!畑被害の特徴と規模を比較
イタチとウサギ、どちらの被害が深刻でしょうか?実は、両者の被害には大きな違いがあるんです。
一言で言えば、ウサギの方が広範囲に被害を与えやすいのですが、イタチは狭い範囲でも集中的な被害を引き起こすことがあります。
まず、食べ方の違いを見てみましょう。
ウサギはガリガリと野菜を齧る感じで、葉っぱや茎を中心に食べます。
一方、イタチはガブリと噛みちぎるように食べ、根菜類や果実も狙います。
「ウサギさんは可愛いけど、イタチさんは怖そう...」なんて印象を持つかもしれませんね。
被害の特徴を比較してみましょう。
- ウサギの被害:
- 広範囲にわたる食害
- 地上部の野菜が主な標的
- 連続的な被害が多い
- イタチの被害:
- 局所的だが集中的な食害
- 地上部も地下部も狙われる
- 不規則な被害パターン
ウサギなら「パリパリパリ」と外側の葉から順に食べていくので、多くの株に軽度の被害が出ます。
一方、イタチは「ガブッ、ムシャムシャ」と一つの株を集中的に食べ荒らすので、被害に遭った株は全滅する可能性が高いんです。
対策方法も異なります。
ウサギ対策では畑全体を囲うフェンスが有効ですが、イタチは木に登れるので、より高いフェンスや天井部分の対策も必要になります。
「うーん、どっちも厄介だなぁ」と頭を抱えたくなりますよね。
でも、どちらの被害も決して防ぎようがないわけではありません。
ウサギもイタチも、それぞれの特性を理解して対策を立てることが大切です。
例えば、ウサギ対策用のネットを張りつつ、イタチ対策として強い臭いの植物を畑の周りに植えるなど、複合的な対策が効果的です。
「よし、ウサギさんもイタチさんも、うちの畑には来させないぞ!」という気持ちで、しっかり対策を立てましょう。
動物たちとの知恵比べを楽しみながら、美味しい野菜を育てていけるはずです。
根菜類vs果菜類!イタチの好み徹底解析
イタチは根菜類と果菜類、どちらが好物なのでしょうか?実は、両方とも大好物なんです。
でも、その食べ方や被害の特徴には違いがあります。
今回は、イタチの食べ物の好みを徹底解析してみましょう。
まず、根菜類についてです。
ニンジン、ジャガイモ、サツマイモなどがイタチのお気に入りです。
「えっ、土の中の野菜も食べるの?」と驚く方もいるでしょう。
実はイタチ、鋭い嗅覚の持ち主なんです。
地中の根菜の匂いを嗅ぎつけて、ほじくり出して食べちゃうんです。
一方、果菜類。
トマト、イチゴ、メロンなどの甘い果菜類も大好物です。
地上にあるので簡単に手に入るし、甘くて栄養価も高いので、イタチにとっては格好のごちそうなんです。
それぞれの特徴を比べてみましょう。
- 根菜類:
- 地中からほじくり出す必要がある
- 栄養価が高く、エネルギー源として重要
- 被害が見つかりにくい場合がある
- 果菜類:
- 簡単に手に入る
- 水分と糖分が豊富
- 被害がすぐに目につきやすい
トマト畑なら「パクパク、ジュルジュル」と実をしゃぶるように食べるんです。
「まるで美食家みたい!」と感心してしまいそうですが、農家さんにとってはたまったものではありませんね。
対策方法も少し違ってきます。
根菜類なら地面に網を敷いてほじくり返しを防ぐ、果菜類なら実を個別にネットで覆うなどの方法が効果的です。
「よし、これでイタチの好物を守れるぞ!」と意気込んでみましょう。
でも、気をつけたいのは、イタチは賢い動物だということ。
根菜類を守りすぎると果菜類を狙うかもしれません。
逆もありえます。
だから、畑全体をバランスよく守ることが大切なんです。
「イタチさん、うちの野菜はどれも美味しくないよ?」なんてごまかしても通用しません。
でも、イタチの好みを知ることで、効果的な対策が立てられるはずです。
美味しい野菜を育てる喜びと、それを守る知恵比べを楽しんでくださいね。
春夏vs秋冬!季節で変わるイタチ被害の特徴と対策
イタチの畑被害、実は季節によって特徴が変わるんです。特に春と秋に被害が増加する傾向があります。
でも、夏と冬にも油断はできません。
それぞれの季節の特徴と対策を見ていきましょう。
まず、春。
イタチにとっては繁殖期の始まりです。
「恋する季節」なんて言うと可愛く聞こえますが、実は栄養を求めて活発に動き回る時期なんです。
新芽や若葉が伸び始める野菜が特に狙われやすくなります。
夏になると、暑さを避けてイタチの活動は少し落ち着きます。
でも、水分の多い野菜を狙って畑に現れることも。
「暑いからイタチも来ないだろう」なんて油断は禁物です。
秋は再び活動が活発になります。
冬に備えて栄養を蓄える時期なので、根菜類や果実を特に狙います。
「実りの秋」はイタチにとっても魅力的な季節なんです。
冬は寒さで活動が鈍るように思えますが、実はイタチは冬眠しません。
暖かい場所を求めて、むしろ人家の近くに現れやすくなることも。
季節別の対策をまとめてみましょう。
- 春:
- 畑の周りにフェンスを設置
- 若い野菜をネットで保護
- 夏:
- 水場の管理を徹底
- 果菜類に注意を払う
- 秋:
- 収穫物の管理を厳重に
- 貯蔵野菜への対策を強化
- 収穫物の管理を厳重に
- 冬:
- 畑の周りの隠れ場所を減らす
- 堆肥置き場や納屋の管理を徹底
でも、季節に合わせた対策をすることで、効率的にイタチから畑を守れるんです。
例えば、春には「新芽を守れ作戦」、夏には「水分作戦」、秋には「実りガード作戦」、冬には「隠れ家撲滅作戦」なんて名付けて、楽しみながら対策を立ててみるのはどうでしょうか。
季節の変化を楽しみながら、イタチとの知恵比べを楽しんでください。
「よーし、今季もイタチに負けないぞ!」という気持ちで、美味しい野菜作りに励んでみてくださいね。
四季折々の野菜の味と、イタチ対策の達成感を味わえる、そんな畑づくりを目指しましょう。
効果的なイタチ対策と有機農法との両立

高さ1メートル以上のフェンスで「侵入を90%阻止」
イタチ対策の王道、それが高さ1メートル以上のフェンス設置です。なんと、これだけで侵入を90%も阻止できるんです。
「えっ、そんな簡単なことでイタチを防げるの?」と驚く方もいるでしょう。
でも、本当なんです。
イタチは賢い動物ですが、高いフェンスを乗り越えるのは苦手なんです。
フェンスを設置する際のポイントをいくつか紹介しましょう。
- 高さは最低1メートル、できれば1.5メートルがベスト
- 網目は2センチ以下の細かいものを選ぶ
- 地面との隙間をなくすため、20センチほど地中に埋める
- フェンスの上部を外側に30度ほど傾けると、さらに効果的
でも、長期的に見れば、収穫量の減少を防げるので十分元が取れるんです。
フェンスの材質も重要です。
金属製が一番丈夫ですが、プラスチック製でも十分効果があります。
木製の場合は、イタチが爪を立てて登りやすいので注意が必要です。
設置後も定期的な点検を忘れずに。
「よし、これで完璧!」と安心していると、小さな隙間からイタチが侵入してしまうかもしれません。
特に、地面との接地部分や支柱周りをしっかりチェックしましょう。
フェンス設置は手間がかかりますが、一度しっかり設置すれば長期間安心できます。
「よーし、わが畑は難攻不落の要塞だ!」なんて気分で、イタチから大切な野菜を守りましょう。
イタチを寄せ付けない「香り強いハーブ」5選
イタチを寄せ付けない強い香りのハーブ、実はたくさんあるんです。これらを畑の周りに植えることで、自然な方法でイタチを遠ざけることができます。
では、イタチ撃退に効果的なハーブを5つ紹介しましょう。
- ラベンダー:甘い香りがイタチの嗅覚を刺激
- ミント:清涼感のある香りがイタチを混乱させる
- ローズマリー:強い香りがイタチを寄せ付けない
- セージ:独特の香りがイタチを遠ざける
- タイム:爽やかな香りがイタチを警戒させる
これらのハーブは、強い香りでイタチの敏感な嗅覚を刺激し、不快に感じさせるんです。
ハーブを植える際のコツをお教えしましょう。
畑の周りに30センチ間隔で植えると効果的です。
「よーし、ハーブの壁で畑を守るぞ!」なんて意気込んでみるのもいいですね。
ハーブは乾燥に強いので、水やりの手間も少なくて済みます。
ただし、日当たりのよい場所を選んでくださいね。
日陰だと香りが弱くなってしまいます。
また、これらのハーブは料理にも使えるので一石二鳥です。
「今日の晩ご飯はミントティーにしよう」なんて楽しみ方もできちゃいます。
ハーブの香りは人間にとっては心地よいものですが、イタチにとっては不快なんです。
自然の力を借りて、優しくイタチを遠ざける。
そんな素敵な畑づくりを始めてみませんか?
木酢液スプレーで「有機栽培にも優しい」イタチ対策
木酢液スプレーは、有機栽培にも使える優しいイタチ対策なんです。自然由来の成分で作られているので、環境にも安全で効果的なんですよ。
「木酢液って何?」と思う方もいるかもしれませんね。
木酢液は、木材を蒸し焼きにしたときに出る煙を冷やして液体にしたものです。
強い酸性の臭いがイタチを寄せ付けないんです。
木酢液スプレーの作り方と使い方をご紹介しましょう。
- 木酢液を水で5倍に薄める
- 霧吹きに入れる
- 畑の周りや作物の近くに吹きかける
- 週に1〜2回程度繰り返す
実は、木酢液には植物の生長を促進する効果もあるんです。
イタチ対策をしながら、野菜の成長も助けられる。
まさに一石二鳥ですね。
使用する際の注意点もいくつかあります。
まず、直接野菜にかけすぎないこと。
野菜に臭いがついてしまう可能性があります。
「せっかく育てた野菜が臭くなっちゃった?」なんてことにならないように気をつけましょう。
また、雨が降ったら効果が薄れるので、再度散布する必要があります。
「あっ、雨が降ったぞ。明日は木酢液スプレーの日だな」なんて、畑仕事の予定に組み込んでおくといいでしょう。
木酢液は園芸店やホームセンターで手に入りますが、自家製も可能です。
ただし、作り方には専門知識が必要なので、初心者の方は市販のものから始めるのがおすすめです。
自然の力を借りて、イタチと野菜の両方に優しい対策。
それが木酢液スプレーなんです。
有機栽培を目指す方にとって、心強い味方になりますよ。
ニンニクとネギで作る「天然の忌避剤」レシピ公開
ニンニクとネギを使った天然の忌避剤、実はとても効果的なんです。イタチの嫌いな強い臭いで畑を守れるんですよ。
しかも、材料は台所にあるものばかり。
簡単に作れて、とってもお手軽なんです。
では、この天然忌避剤の作り方をレシピ形式で紹介しましょう。
- ニンニク3かけとネギ1本をみじん切りにする
- みじん切りにしたものを1リットルの水に入れる
- 一晩置いて成分を抽出する
- ざるでこして、液体だけを取り出す
- 霧吹きに入れて完成!
本当に、これだけなんです。
台所にある材料で、誰でも簡単に作れちゃいます。
使い方も簡単です。
畑の周りや作物の近くに吹きかけるだけ。
イタチの通り道になりそうな場所を重点的に吹きかけるのがコツです。
「よーし、今日はイタチさんの通学路にスプレーだ!」なんて感じで楽しみながらやってみてください。
この天然忌避剤、イタチ対策以外にも効果があるんです。
害虫よけにも使えますし、野菜の病気予防にも効果があるんですよ。
まさに一石三鳥。
「すごい!台所の救世主じゃん」なんて感動してしまいそうです。
ただし、注意点もあります。
強い臭いなので、使用後は手をよく洗いましょう。
目に入らないように気をつけることも大切です。
「うわっ、目にしみる?」なんてことにならないようにね。
また、効果は1週間ほどで薄れるので、定期的に作り直す必要があります。
でも、材料が安いので、コスト的にも優しいんです。
「毎週の畑仕事の前に、忌避剤作りをするのが日課になっちゃった」なんて人もいるかもしれません。
自然の力を借りて、優しくイタチを遠ざける。
そんな素敵な畑づくり、始めてみませんか?
驚きの効果!「古いCDの反射光」でイタチを撃退
古いCDの反射光でイタチを撃退できるんです。意外かもしれませんが、これ、本当に効果があるんですよ。
しかも、お金をかけずにできる方法なんです。
「えっ、CDでイタチが逃げるの?」と思う方も多いでしょう。
実は、CDの反射光がイタチの目を驚かせるんです。
イタチは夜行性で光に敏感。
突然の光の動きに警戒心を抱くんですね。
では、具体的な方法を見てみましょう。
- 使わなくなったCDを用意する
- CDに穴を開けて、紐を通す
- 畑の周りの木や支柱にCDを吊るす
- 風で揺れるようにして設置する
本当に、これだけなんです。
家にある古いCDを再利用できるので、エコにもなりますね。
設置する際のコツをお教えしましょう。
CDは1メートルおきくらいに吊るすのがいいです。
そして、高さは地面から50センチから1メートルくらいの範囲で。
「よーし、我が畑はディスコ会場だ!」なんて楽しみながらやってみてください。
CDの反射光は日中も夜も効果があります。
日中は太陽光を、夜は月光や街灯の光を反射させるんです。
24時間体制でイタチ対策ができるなんて、すごいですよね。
ただし、注意点もあります。
強風の日はCDが飛ばされないように、しっかり固定しましょう。
「あれ?CDどこいっちゃったの?」なんてことにならないようにね。
また、定期的にCDの表面を掃除するのも大切です。
ほこりや虫の死骸でくすんでしまうと、反射効果が弱くなってしまいます。
「週末はCD磨きの日!」なんて、畑仕事の予定に入れておくといいでしょう。
古いCDが宝物に変身。
そんな驚きの方法で、イタチから畑を守ってみませんか?
環境にも優しく、コストもかからない。
まさに一石二鳥の対策方法なんです。